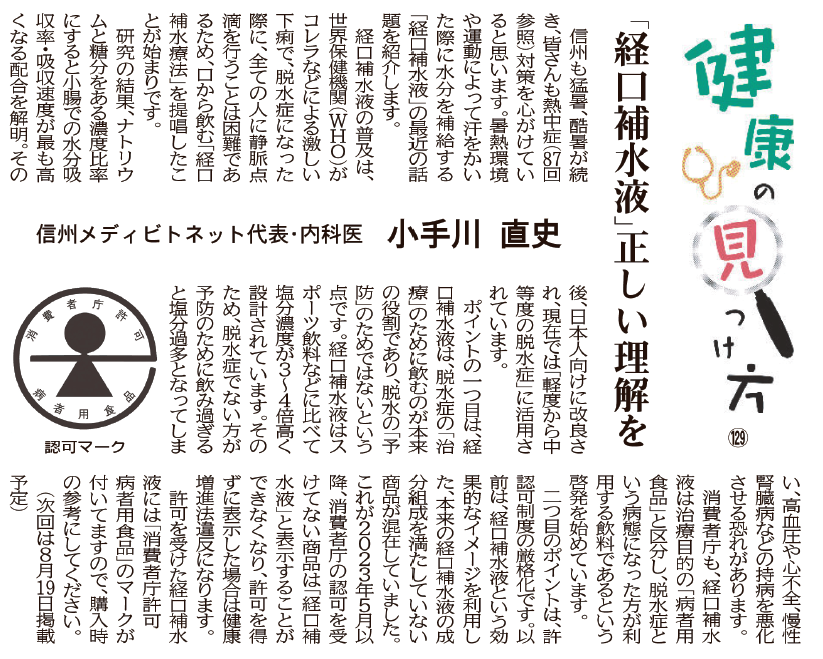信州も猛暑、酷暑が続き、皆さんも熱中症(87回参照)対策を心がけていると思います。
暑熱環境や運動によって汗をかいた際に水分を補給する「経口補水液」の最近の話題を紹介します。
経口補水液の普及は、世界保健機関(WHO)がコレラなどによる激しい下痢で、脱水症になった際に、全ての人に静脈点滴を行うことは困難であるため、口から飲む「経口補水療法」を提唱したことが始まりです。
研究の結果、ナトリウムと糖分をある濃度比率にすると小腸での水分吸収率・吸収速度が最も高くなる配合を解明。
その後、日本人向けに改良され、現在では「軽度から中等度の脱水症」に活用されています。
□
ポイントの一つ目は、経口補水液は、脱水症の「治療」のために飲むのが本来の役割であり、脱水の「予防」のためではないという点です。
経口補水液はスポーツ飲料などに比べて塩分濃度が3~4倍高く設計されています。
そのため、脱水症でない方が予防のために飲み過ぎると塩分過多となってしまい、高血圧や心不全、慢性腎臓病などの持病を悪化させる恐れがあります。
消費者庁も、経口補水液は治療目的の「病者用食品」と区分し、脱水症という病態になった方が利用する飲料であるという啓発を始めています。
□
二つ目のポイントは、許認可制度の厳格化です。
以前は、経口補水液という効果的なイメージを利用した、本来の経口補水液の成分組成を満たしていない商品が混在していました。
これが2023年5月以降、消費者庁の認可を受けてない商品は「経口補水液」と表示することができなくなり、許可を得ずに経口補水液と表示した場合は健康増進法違反になります。
許可を受けた経口補水液には「消費者庁許可 病者用食品」のマークが付いてますので、購入時の参考にしてください。
(2025年7月29日(火)付MGプレス「健康の見つけ方」から)