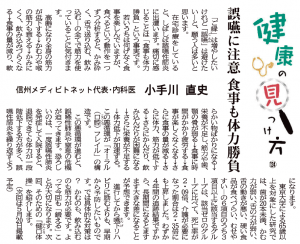「ご縁」は増やしたいけれど「誤嚥」は避けたい」ーと、願う人は多いと思います。
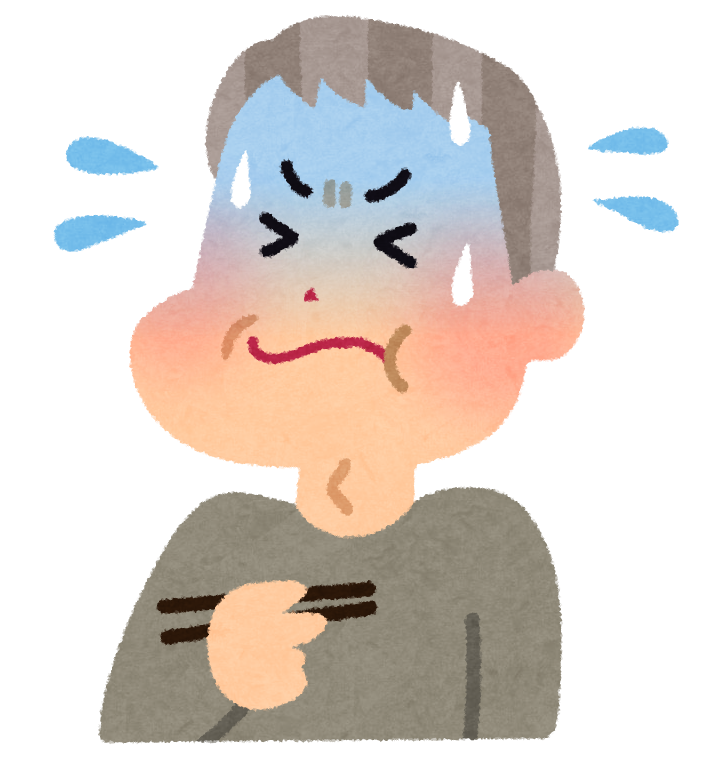
在宅診療をしていると、しばしば誤嚥性肺炎に出遭います。
痛切に感じることは「食事も体力勝負」だという事実です。
□
若いうちは何げなく食事を楽しんでいますが、食べるという動作を一つずつ分析すると、かみ砕く、舌で送り込む、飲み込むーの全てで筋力を使っていることに気付きます。
高齢になり全身の筋力が低下する
→かむ力や喉の筋力も衰え
→かみにくく、飲み込みづらくなる
→食事の量が減り、軟らかい物ばかりになる
→栄養が不足し、筋力や歯、顎の骨が弱る
→食事に時間がかかり疲労する
→食事が楽しくなくなる
→さらに食事の量が減る
→さらに体力、筋力が低下する
→さらにかんだり、飲み込んだりが困難になる
→さらに栄養が不足する
→体力低下が加速する。
この悪循環が「オーラル(口腔)フレイル」の構造です。
□
この悪循環が進むと、誤嚥性肺炎や窒息の危機が迫ってきます。
恐ろしいのは、一度誤嚥性肺炎を発症して入院すると、退院できても体力が一段階低下する方が多く、誤嚥性肺炎を繰り返すようになります。
東京大学による65歳以上を対象にした研究では、歯が20本未満、かむ力が弱い、舌の力が弱い、舌の動きが悪い、硬い食品が食べづらい、むせやすいーの6項目のうち3項目以上に該当するグループは、該当ゼロのグループに比べて、死亡率が2.09倍、介護が必要になった割合は2.35倍にも上昇しました。
わずか4年間の追跡結果ですから、長期間になるとますます大きな差が開くことが予想できます。
進行してから嚥下リハビリに励むよりも、早期から予防したいものです。
具体的な対策は?
かむのも、飲み込むのも筋力が必要です。
よって今回も「鍛える」ことが大切になります。
次回、そのための「健口体操」を紹介します。
□
(2025年4月29日(火)付MGプレス「健康の見つけ方」から)